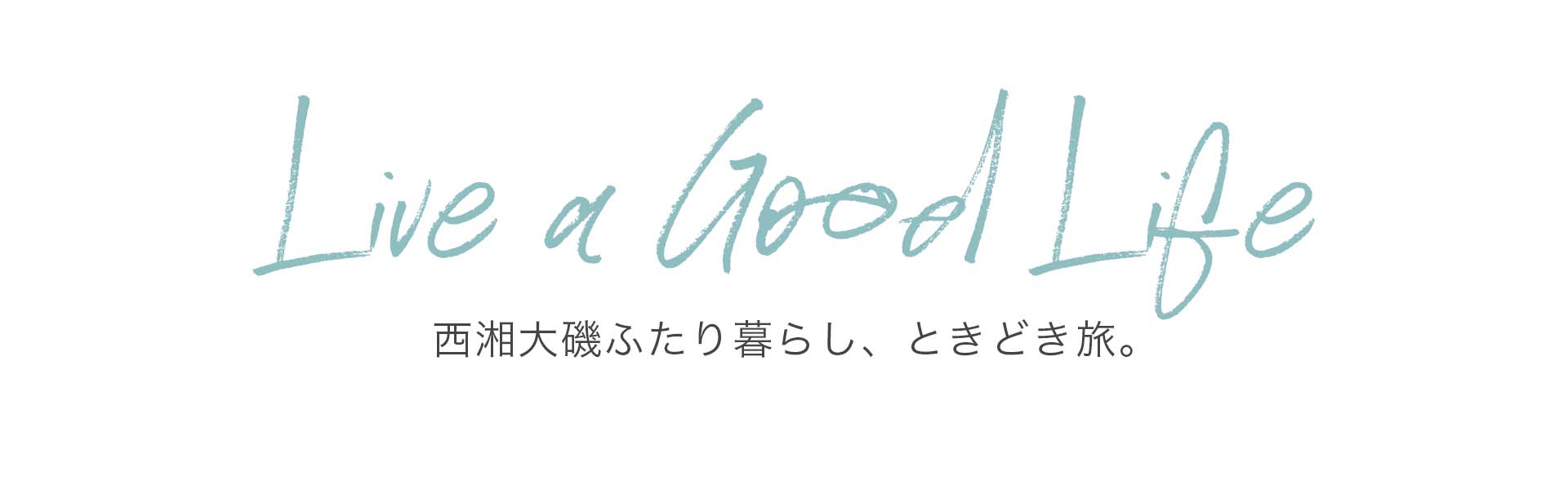秋も深まってきました
11月も半ばを過ぎ、だんだん桜の木などの葉は紅葉したり落葉がはじまったりしています。
そして、野鳥観察のシーズンはこれからが本番。なぜなら、夏の間は木に葉っぱが生い茂っていて見づらかった小鳥たちが、葉が落ちることによって見つけやすくなるから。また、冬鳥と呼ばれる冬になると北から渡ってくる鳥たちが見られるようになります。季節によって見かける野鳥が違うというのもなんとなくしか知らなかった知識。日本で見られる野鳥には、見られる季節によって夏鳥、冬鳥、留鳥といった区別があるのです。

金目川(花水川)河口にぶらりお散歩
大磯町と平塚市の境あたりを流れている金目川。その河口あたりから海に抜けるルートはわたしのお散歩コースのひとつ。なるべく川べりを歩いて川辺にいるトリ🐦を愛でながら歩くことも多いです。

冬の風物詩ーカモの姿が増えてきました
カモって冬に多いなーという認識はありましたが、実はカモ科の鳥たちは、ほとんどが冬の渡り鳥なんですね。通年いるのはくちばしの先が黄色いカルガモだけ。その他のカモやガン、ハクチョウといった鳥たちは、はるかシベリアあたりから飛んできて、冬の間、日本の河川や池に留まるのです。

カモの種類はものすごく多い
カモとひと口に言っても、実はカモ類ってすごくたくさんの種類がいるんです。カモといえばカルガモくらいしか名前を知らなかったわたしですが、調べてみると、すでにいろんなカモさんたちが川にやってきていることがわかりました。

カモ類は、ガンカモ類のなかで一番小さいグループで、一般的にオスは目立つ派手な羽色、メスは地味な羽色をしています。カモ類は、基本的に毎年つがい相手を替えます。
『知って楽しいカモ学講座』より
カモ類は、食物をとるときに水に潜らない種と水に潜る種に分かれていて、それぞれ「水面採食性カモ類」と「潜水採食性カモ類」というふうに分類されています。
カモってめちゃくちゃいっぱい種類がある上に、同じ種でもオスとメスで全然色が違うし、繁殖期とそうでない時期でもまた全然色が違ったり、冬になると衣替えみたいに変身するのだけれど、その羽が抜け落ちたり生えたりする期間をエクリプスと呼んで、また見え方が違ったりするからややこしい。
でも小鳥と違ってある程度大きさがあってそれほど逃げないため、写真は撮りやすい。なので望遠でいろいろ写真を撮ってあとからこれは何カモ?って判別する楽しさがあります。


金目川河口では、その他今までに、マガモ、カルガモ、オオバンなどを見ました。季節が進むともっといろいろ見られるのかな?これから冬のシーズンが楽しみです。
日本のカモについてお勉強
カモの分類や生態についてはこんな本を(図書館で借りて)読んでみました。識別についてはMerlin Bird IDという野鳥の分類記録アプリも活用してます。アプリについてはまた別途ご紹介する予定。
河原の草の上で様子をうかがうモズ
ぼんやり歩いていると視界に茶色い鳥が飛んでいるのを見つけました。止まった先をみると…

秋以降によく縄張りを主張して高鳴きをするモズがあたりの様子を伺っていました。

ちなみにかなり遠くにいて、望遠最大限&トリミングしてこれ。撮影前に双眼鏡でのチェックは欠かせません。
金目川河口の中洲にいるのは・・・
海が広がる河口にやってきました。中洲に黒い点が見えます。


カワウでした!鵜は羽が濡れると水を弾かないので?こうやってたまに羽を広げて乾かしているのだそう。

カワウが泳いでるときの様子はこんな感じ。

鳥に興味を持つ前は、ただぼんやり川にカモがいるな〜と素通りするだけでしたが、興味を持って細かく見ていくといろんな知らないことやおもしろさを発見できてうれしいですね。この記事を書くためにまた少しカモのことを調べたりして、またひとつかしこくなりました笑。